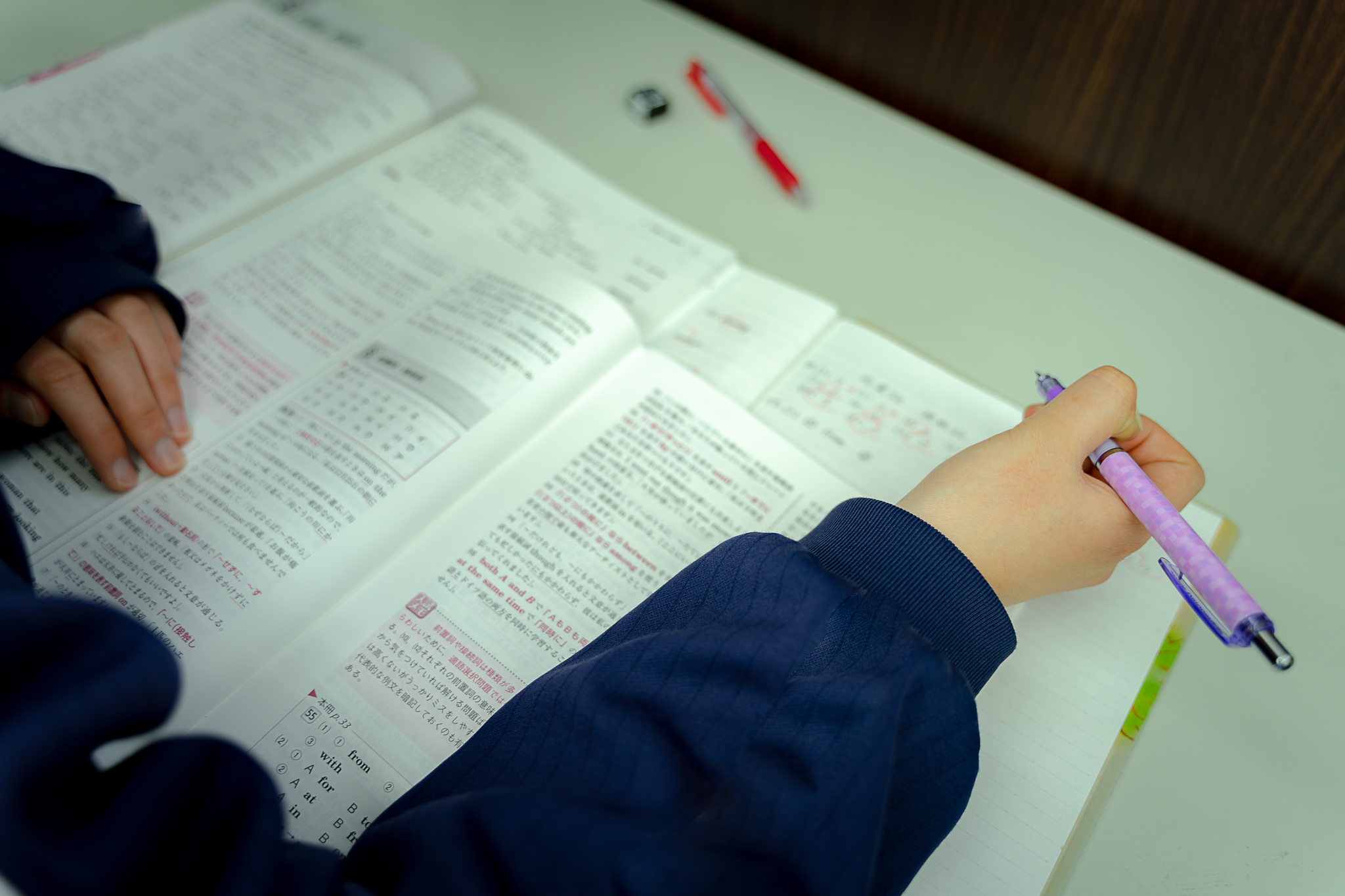こんにちは!関東ではすっかり暖かくなったかと思えば急に雪が降る地域もあり、なんだか落ち
着かない天気ですね。季節の変わり目ですのでみなさま、体調には十分ご注意ください。
さて、いよいよ新年度がスタートしました。中学生になった生徒さん、あるいは高校生になった
生徒さんが入学式後に報告に来てくれました。真新しい制服がなかなか似合ってましたよ!
新学年にあたり、みなさんは勉強はどうでしょうか?特に小学生から中学生になると、学習の進
度が早くなり内容もかなり複雑になります。しっかりした勉強の準備はできていますか?
実は春期講習で少しおもしろいことがありました。当塾の小学生はほぼ全員英語の勉強をしてい
ます(理由は過去のブログを見てください)。今回、ある生徒のお友達が無料体験を受けたのです
がやはり単語を書くというのがなかなかできません。一方、当塾の生徒は中学の教科書をす
らすら読み、さらに訳もできていましたので、お友達はかなりびっくりした様子でした。何も特
別に頭が良いわけではなく、しっかり時間をかけて中学英語の準備をしてきただけです。
小学生のうちは習い事をやらせて、中学生になったら学習塾とお考えの保護者の方は多いと思
いますが、もう英語に関してはそうも言っていられません。圧倒的な差がついています。将来の
ことを考えるなら、大学までは英語は重要科目であると感じています。新中学生のお子さんをお
持ちの保護者のみなさん、ぜひお子さんの英語力の強化と早い段階での英検等の資格取得を当塾
にお任せいただければと思います。無料体験も随時行っております。ただ通わせるだけでなく学
習・生活・進路の3つの柱を中心に、お子様の大切な成長過程をブラッシュアップするお手伝い
をさせていただければ幸いです。ぜひお気軽にお電話、ご来塾お待ちしております。